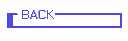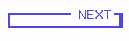............................. .............................竣工時の外観(「逓信省の建築」(張菅雄)より) |
 2008年1月撮影の送信所現状 |
■ねらいと方法 検見川送信所を守り、再生再活用に向けてた動きが活発になってきた。この建物は、日本においての国際通信 を目的とした、本格的な通信施設建築として希少であるばかりか、吉田鉄郎の若き日の作例としても数少ない 残存例でもある。 |
 ............................. .............................竣工時の外観(「逓信省の建築」(張菅雄)より) |
 2008年1月撮影の送信所現状 |
しかし現在の姿は、見るに忍びないほどの劣化ぶりである。吉田鉄郎の真骨頂たる繊細な造形感覚の多くは、重 くのしかかる廃墟のイメージの陰に隠されてしまっているのではないかと思った。先日、「検見川無線送信所を 知る会」でこの建物の価値について話す機会を持った(#1)。しかし、実物が時を経て変化してしまうと、優れた 造形性をいくら言葉で訴えても、もどかしさを感じざるを得ない。 そういった訳で、より具体的に吉田鉄郎の造形を探り浮き彫りにしてみる必要を感じ、この際、竣工当時の建物 の外観はどのようなものであったのか、CGを使って再現することを思いついた。 方法は、現地に赴いて主に正面部分など一部実測を行い、あとは、文献に掲載されていた1/100の平面図や私の 撮った写真の他数々の写真をもとにして寸法関係を割り出したり、再現を行うための資料とした。 ソフトは、CG2000とフォトショップを併用した。細かいアールなどディテールの大半はフォトショップによる 手作業となり、かなりの手間を要した。 やや手前味噌的な言い方だが、それでも結果は、思った通りのモダニズムを強く志向した建物だった、というの が私の率直な感想である。しかも流行に乗った借り物のモダニズム建築ではなく、現出したのは、他のどこにも 類を見ない世にも稀な美しさを湛えた建物であった。―私にはそう思えた。 |
#1:「私の見た逓信省吉田鉄郎の検見川送信所」(2007.10,PDFファイル) |

その他、下記の考え方に基づいて作図した。 ・現在では姿を消した付属舎や昭和8年の増築建物は再現しなかった。また再現するに足る資料も手元には無い。 しかし地面におよその位置に痕跡を加えた。 ・鉄塔や空中線は描かなかった。こちらも再現出来るだけの資料は持っていない。 ・デザインが不明の出入り口開口部は、大きさは平面図を参照しつつ、窓付きフラッシュ戸とした。判明次第修 正することにしたい。 ・長い歴史を経た建物であり、いくつかのエピソードを暗示するべく点景として描き込んだ。 −点景その1:昭和4年のドイツの飛行船ツェッペリン伯号の飛来は、8月19日に飛行船が東京に突 如姿を見せるなど大いに話題となった。この日本の通信技術をアピールする好機に各局が競って 交信を試みたことが記録されている。根室の落石局に続いて、検見川送信所を含む東京無線電信 局でも交信に成功したとの記録が残る(「日本無線史」第4巻p.277)。従って、実際に検見川上 空を飛行していたか定かではないが、点景に加えてみた。 −点景その2:建物の廻りは、戦後のある時期には、植栽として桜と松によって彩られていたとの 当時の職員の証言があるので、遠景に配してみた。 |

■外壁面の仕上げ 現地で建物の外壁を見てみると、全体が白い粒状の石で覆われていたことがわかる。掻き落したように少し荒 い仕上げだが、逓信局舎建築でよく用いられていた、通称「擬石洗い出し」に近い仕上げ方と考えられる。白 色の石は寒水石と思われモルタルに混ぜて塗られていたようである。少なくとも、当初は、現在の暗く汚れた 外観からは想像も出来ない位、白く輝く建物であったと言える。 また、タイルなどで構造体を覆うことなく、左官仕上げによって鉄筋コンクリート造らしさ損なうことなく表 現したことは、(建設費用などの経済的制約とは別に)デザイン上意図されたものであったに違いない。 |

■通信施設というビルディングタイプへの、鉄筋コンクリート建築による模索 無線通信技術は1895年にマルコーニによって発明され、日本も含めて世界的に急速な発展を遂げた先端技術で あった。特に第一次世界大戦後、言うまでもなく国際間のコミュニケーションは重要さを増し、また軍事利用 の思惑も重なって、遠距離無線通信技術は国際的な需要の増大と発展にはずみをつけていたのである。 しかし、吉田が送信所の設計を始めた頃、当時の最先端テクノロジーがもたらした無線通信局なるビルディン グタイプのデザインについては、未だ手付かずの状態であったようだ。わずかにオランダのコートワイク放送 局(Radio Kootwijk)が傑出した建物として、またアムステルダム派に属する建築として1922年に建てられて いた。 |

通常アムステルダム派の建築は、煉瓦など伝統的素材を用いた表現主義的なデザインを特徴とするのだが、こ の放送局はその中で、例外的にコンクリートという近代建築の素材をそのまま表現しているとの考え方もある (#2)。 逓信省の技師として、また海外からの文献をうず高く製図版の脇に積んで設計に励んだとされる吉田鉄郎なら ば、オランダのこの建物について承知していたと考えた方が自然だ。ドイツ表現派的に中央に塔を持つ対称な ファサード、コンクリート壁面をむき出しにしてその可塑性を最大限に前面に打ち出すデザインなどの点で、 大いに参考にしたのではないかと推測される。 さらに検見川送信所以後に建った依佐美送信所(最近取り壊されてしまったが)も同様、このオランダの放送 局からの影響を感じさせる。 |
#2:「近代建築史」(石田潤一郎,中川理編,昭和堂,1998年)中、 梅宮弘光氏がコートワイク放送局について記述している。 |

■窓開口部−逓信省標準スタイルからアムステルダム派建築へ 検見川送信所のCGパースを描きながら、いくつも連続した窓が建物のデザインを大きく左右する要素である ことに気付かされた。 縦長窓を組み合わせて配列した点だけをとってみれば、逓信省による電話局舎などの標準設計を踏襲しており これと変わらない。一官僚としての吉田にとってみれば、標準設計を逸脱することは基本的に許されなかった のであろう。標準設計とは、膨大な設計業務量を能率的にこなすために当時の逓信省営繕課の和田信夫らが推 進したとされ、特に関東大震災以後の事例では、通常縦長窓が2,3個セットで間に柱形が挿入され凹凸を付 けただけの外観となることが多かった。 しかし歴史様式建築を極端に簡略化したことによってもたらされるデザインは、必要最小限の威厳を与えるだ けで先進性に乏しいものであった。 |

普通に縦長窓を用いれば、こうして様式建築風に堕してしまうところであるが、しかし検見川送信所の窓は、 まず、無装飾で柱型も無い平坦な壁面にリズミカルに配されている。 そして注意すべきは窓の棧で、ほぼすべて横桟として執拗に何段も平行して繰り返されている。横棧は白っぽ く塗装され、明らかに水平ラインを強調する意図が働いていたことがわかる。窓周囲四方を見ても、縦方向の エッジラインはアールとしてわざとぼやかされている。逆に横方向のエッジはほぼ直角のままで、陰影が水平 ラインだけを強調されている。 ―威圧的な垂直性から軽快な水平性へ。こうして、吉田は、窓のデザインにちょっとした配慮を行ったことで、 あたかもモールス信号の如くにリズミカルで軽やかな水平的な印象を持つ外観全体のイメージへと転化させて しまった。軽快なデザインはモダニズムの求めるところであり、これを知る吉田鉄郎は意図して行ったに違い ないであろう。 この発見は、今回CGを描いた中でも大きな収穫だと感じた。この考えがそう間違ってもいないならば、吉田 がその後行った東京中央郵便局の設計などと共通した、すなわちちょっとした細部のデザインが外観全体を決 定付けるという吉田の真骨頂たる造形方法が、ここで既に萌芽していたとも言えよう。 ここで思い出されるのが、アムステルダム派のデ・クラークらによる集合住宅に見られる窓のデザインである。 これらは、表現主義的な煉瓦の造形とコントラストをなすように、白く軽快な横棧付の窓が印象的に並べられ ており、吉田もこれをヒントにしたのではないかとの想像が働く。 本来、吉田鉄郎のアムステルダム派への関心は強かったようで、例えば京都中央電話局で、煉瓦タイルをバラエ ティーに富んだパターンで貼り分けたことは、このことを示す好例であろう。 |
 .....................
.....................
■謎の北側の開口部 北側の開口部はどうもはっきりしないことがある。 際立つふたつの大型アーチ窓の頂部が一部平らになっているが、吉田の意図通りのものであったのかどうかに ついて、私は当初疑いを抱いていた。だが、アムステルダム派の建築物を思い浮かべれば似たようなデザイン の窓があることから、一応は納得した。 しかし私が過去に撮った写真では、方立て(窓の中の柱状の部材)が1〜2階連続しているように見える。現 在は鉄板で覆われており尚更分からなくなっている。もしも、この大きな窓が上下階で連続した、いわばカー テンウォールを形成していたとすれば、当時の技術からすれば大胆な試みだったと言えよう。しかも木製で。 今の段階では、どう納まっているのか皆目見当が付かないながらも、窓枠が連続するイメージで描いてみた。 因みに同僚山田守は、大規模なパラボラアーチのカーテンウォールを東京中央電信局の中で設計しようとした 際、上司から却下された経緯がある。代わって吉田が木製で試みたのでは?−との憶測を呼ぶ箇所でもある。 北側中央の1,2階の出入口状の開口は、後に増築が行われた際の渡り廊下の出入口にあたる部分で、改造されて このようになった可能性も考えられる。当初の平面図を見ても判然としないので、仕方なくCGには窓付きの ドア(2階は荷揚げ目的と想定)を描き込んだ。 |

■表現主義風(=分離派風)な特徴について 無線通信は、異なる役割を担った隔たって建ついくつかの施設が協力して、まとまった業務を行うという特質 がある。 検見川無線送信所の業務上の位置付けは、送信を行うための一つの分室であり、本拠は麹町区銭瓶町(当時の 町名)の「東京無線電信局」として、吉田の同僚山田守の設計によって大正14年に竣工した東京中央電信局内 に置かれていた。同じく山田守設計による大正13年竣工の岩槻受信所も受信業務を行う分室であった。 「東京無線電信局」とは、各分室を統括する呼称として、それまで国際通信を行っていた海軍船橋送信所の後 継局として開設されたもので、さらに磐城無線局の業務も引き継ぐなどして国内最大の通信施設となった(#3)。 検見川送信所に先立って建てられていた東京中央電信局は、山田守によるパラボラアーチを多用し分離派建築 の代表格とされた建築であり、岩槻受信所も山田が設計したアーチ窓や曲面を多用し、いずれもドイツ表現主 義(あるいは分離派風)の特徴を強く持っていた。最後に残った検見川送信所だけを、なぜか吉田鉄郎が担当 することになったわけだが、彼の胸中には3件の建物を通信機能を担うデザインとして統合しようという意識 が働いたと察せられる。機能とデザインの一致・・・、普通に考えても、設計者ならばこの点は考慮して然るべ き事柄であろう。こうして送信所にも前2件同様、外壁に曲面多用したりパラボラアーチ窓をあしらった山田 守の建築と見まがうような表現主義風(=分離派風)デザインが取り入れられたものと考えている。 表現主義風デザインについては、吉田鉄郎も既に京都新上電話分局などで取り入れており、意外と躊躇するこ となく行われたものと考えている。 最後にもうひとつ、吉田ならではの繊細なディテール処理を挙げてみたい。出隅を丸くしているだけでなく、 建物全体を通して、最上部の外壁面(パラペット部分に相当する辺り)を微妙に傾斜させている点である。空 に溶け込むかの如く、高くなるに従って先細り的に薄くなる壁断面形状を成し、天端形状は輪郭を消し去るが 如く丸くなっている。建物の視覚的な重量感や威圧感を和らげる工夫であり、コンクリート建築の黎明期にあ って、施工する人々にとってみれば訳も分からぬまま相当な手間を余儀なくされたものと想像される。 それでも微妙なデザインに気を遣い実行するという、妥協を許さない吉田の姿勢が、こうしたディテール処理 からも感じ取ることが出来る。 |
#3:「日本無線史」第4巻(電波監理委員会,S26)P.70,P.234などに、東京無線電信局の記述あり。 |
■送信所の立地 下の図は、松井天山が昭和5年に描いた検見川鳥瞰図であり、送信所も丁寧に描かれている。これによれば、 当時の建物は、4方に入口をもつ囲い塀の中に配置されていたことになる。 |
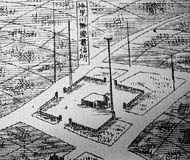
松井天山の配置を参考にすると、さしずめ下の図のようなイメージとなろうか。周囲は一面の甘藷畑であった らしい。 |

こうして、不完全ではあろうとも、CGの作成を通して吉田鉄郎の設計に対する考えの一部を追体験したこと は、私にとって有意義な経験となった。 拙い画像ではあるが、建物の価値を再認識するための資料の一部となれれば幸いである。(#4) よみがえれ!、検見川送信所。 |
#4:当方私製これらのCGについては、検見川送信所の価値を認め、保存・活用に賛同する 方であれば、承諾なく転載して頂いて構いません。 (ご連絡頂ければ、必要によって原寸データの提供も可能です。) |
(以上 2008年1月 記) |