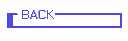パース (「建築世界」1920(大正9)年11月号から)
大正9年に逓信省営繕課に入省した森泰治の存在は、同期に入省した山田守の活動にかくれまた逓信省の視点
からしか存在が語られざるを得ずにいた森泰治の本来の作風や実際の設計活動を知る上で、逓信省入省直前
の卒業制作案及びと大正15年に逓信省を去り宮内省内匠寮に籍を移した後の作品を取り上げることにした。
森泰治は宮内省技師として昭和2年に多摩御陵の造営に関わったこと,昭和16年に木造の皋水(こうすい)
記念図書館の設計を行ったことを独自に見出した。
また最近の専門家による宮内省書陵部の図面が調査された結果、学習院昭和寮(現・日立目白クラブ)が森泰
治が技師として設計に携わっていたことも明らかになった。
(2006年 記)
|

森泰治が卒業制作として提出したものである。 作風としては当時日本を席捲していたゼツェッション風で手堅くまとめられたものである。 水彩でパースを描いた点も注目すべきであろう。着彩は想像で補うしかないもののゼツェッション的なイメ ージ打ち出していたものと想像される。軽快でありながら達者な筆致で描かれており、こうした柔らかな詩 情を漂わせる表現は当時の学生の作としては新鮮だったのではないだろうか。 造形手法としては、歴史主義の範囲に留まりながら縦長のプロポーションを基調に建物随所で曲線を用いて いるが、逓信省以後もそのまま設計に活かされ森にとっての指向は概ねこの時点で確立していたように思え る。特に正面の部分で左右にシンメトリックにアーチ付の縦長窓は、森が逓信省を去る直前に設計した大阪 中央電話局の正面を想起させ、森泰治にとってのこだわりが感じられる。 |
●雑感 大正9年に森と山田はいずれも卒業を果たし逓信省に赴いたのだが、同年の「建築世界」誌は二人の因縁を 暗示させる。11月号において様式を器用にアレンジしたこの森泰治の卒業設計案が秀作として掲載されて いるが、同号では山田守は構造派の先輩野田俊彦に論争を挑んでいる。また遡る3月号では山田は分離派旗 揚げ時期にあたり誌上でも気炎を吐く。「建築実態の研究に着目して建築観念を向上せしめよ」の中で形骸 化した様式をもてあそぶ時代状況を強い口調で批判している。まさに森泰治の姿勢とは対称的である。 こうした水と油の二人が同じ仕事場で机を並べようとする門出の年に、同建築誌は先行き案じられる二人の 差異を記録していたことになる。 (2006年 記) |
2005年12月刊行の「皇室建築 内匠寮の人と作品」によれば学習院昭和寮(現・日立目白クラブ)の設計を 森泰治の設計としている。(設計時の図面タイトルは「目白学習院青年寮」) この建物はこれまでは宮内省内匠寮の設計による昭和3年竣工の建物として、今も当初の姿を保ち都選定 歴史建造物に指定された建物として知られる。設計は大正15年に行われており、森が逓信省から異動し た年にあたる。図面押印欄には技師森泰治の判が押されていることが設計担当者特定の決め手となった。 (設計者を権藤要吉と推定される向きもあったが彼の設計への関与は図面上みとめられなかったらしい。 恐らく朝香宮邸のために1925年パリのアール・デコ博視察に赴いていたのかも知れない) |
 ...
... ...
... ...
...
●日立目白クラブ観察記 しかしこの調査を信ずるとして、建物が与える雰囲気の大きな変化はどう説明されるのであろうか。 逓信省時代のゼツェッション風などのドイツ系の重厚な雰囲気は様変わりして、白いスパニッシュ・ス タイルの明るく肩の力の抜けたような軽快さを漂わせている。 森は需要に応じてどの様式でも器用に使い分ける巧みさが彼の持ち味だったと説明してしまえばそれま でだが、そう片付けてしまう前に私なりに外観を観察した。 森の建物は逓信省時代はアーチ付窓を二つでセットにして配置しポイントを作ることはよく行っていた が、ここではアーチ付の縦長窓を三つ並べた非対称な構成をとっている。これは静的安定感よりもリズ ミカルな印象を生む。この建物のデザインを大きく特徴付けている点であり、恣意的になされたのであ ろう。まず目に付く正面の高さの違う3つの縦長窓は、段階を付けて空に迫り上がる動的な印象をもた らす。パラペットの上端がアールである点はスパニッシュスタイルでも使える仕様なので自然と行われ たのであろう。 玄関ドアのアールヌーボー的な装飾については、スパニッシュ調に破綻をもたらしているようだがそれ 以上言及できない。 煙突頂部のイタリア城郭風の装飾(ロンバルディアバンド)は、地中海風のテイストを補強するもので あろう。 |

●気になる小さな装飾 さて、裏口へ廻るとアーチ付の曲面の庇の両入り隅に例のロンバルディアバンドの形状が三段ほど迫り 出すように重なる異様に小さな装飾を見つけた時は一瞬驚いた。隠れひそむような小さな装飾を見て、 なんとなく森泰治に出会ったような錯覚を覚えた。 この装飾はH・ペルツィッヒによるドイツ表現主義の建物ベルリン大劇場の鍾乳石のつららが密集したイ メージに類似している。私が驚いた点は、スパニッシュスタイルで統一された外観の裏側にドイツ表現 主義の要素を意味深気に忍び込ませたことの発見もあるが、しかしより不思議なのはこの装飾の迫り出 すようにパターンを重ね合わせる造形作法に対してである。しかもどこかで見た感覚である。 |
 (下関第一別館の持ち送り装飾) |
それは逓信省による大正12年竣工の電話局で設計担当者不明の下関電話局(現・下関市役所第一別館) 内部の梁下に取り付けられた「持ち送り」と呼ばれる装飾材が脳裏をかすめた。 歴史様式的な雰囲気を残しながら装飾を幾何学的パターンとして単純化し、さらに迫り出すように数段 重ねたユニークな形状をしたもので、当時第一別館の保存運動に関わる方が撮った映像を見て、こうし た装飾を生み出す感性を持った人はそうはいないだろうと感じたものだ。日立目白クラブでみつけたも のとこうした作法が共通している。学習院昭和寮と下関電話局のに共通点はあるのだろうか。 (2006年 記) |