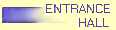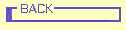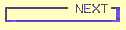分離派建築博物館--各地の建築物--
復興都市に花開くロマン -1- 〜震災復興を契機に建てられた公的施設など〜
1923(大正12)年9月に東京及び近郊を襲った未曾有の大地震で焦土と化した地を復興させるため、都市計画に基づいた
公的都市基盤の再構築が行われた。現在の主要な道路や橋梁など現在の首都の骨格は概ねその当時に形作られたと言って
も過言ではない。復興は内務省復興局などが主導する形で進められたが、概観すれば官民問わず多くの無名の若手設計者
までが関与する一大事業であり、細部まで目を凝らせば自らの理想を込めて分離派や表現主義など様々な新傾向のデザイ
ンが帝都にちりばめられていったことが分かる。
復興期のデザインに対する考え方は明治期までの国家の権威を印象づけるような装飾の多い古典主義的傾向から、より
耐震化などの防災面と共に公共性が重要視されのだが、このことは機能美を求めるモダニズムへの移行を促進させる契機
ともなった。
法恩寺橋
設計:復興局............................場所:東京都墨田区......................................建築年代:1925(大正14)年頃................................................現存


かつて隅田川の支流、墨田区を南北に流れる大横川に架かる橋のうちのひとつであったが、現在
は大横川親水公園に架かる橋のとして整備が済んでいた。
本来橋のたもとにあるだけのはずの親柱が、放物線状の幾何学的オブジェとしていくつもリズミカ
ルに繰り返されている。当時の橋としてはかなり斬新なものだったに違いない。
嵌め込まれている装飾格子は、波を図案化したものか・・。


こうした放物線形状の繰返しは、同じ頃完成した分離派の山田守の東京中央電信局を連想さ
せる。逓信省でこれを設計した山田守は震災後に復興局橋梁課嘱託の命を受け、山田の配下にあ
った山口文象(当時岡村蚊象)が嘱託技師の立場で実際に多くの橋の設計に携わったことが知ら
れている。山田の作風が橋を設計した山口に何らかの形で伝えられ反映されたことは想像に難く
ない。
千代橋
設計:復興局............................場所:東京都中央区......................................建築年代:1926(大正15)年................................................現存(復元整備による),撮影2006年
 竣工当時の姿(「建築写真類聚」より)
竣工当時の姿(「建築写真類聚」より)
放物線形モチーフの反復による親柱付近の造形は、山田守の分離派建築の代表作である東京中央
電信局頂部のミニチュア版と言って良い位よく似ている。
また、法恩寺橋と同様親柱部分がリズミカルに反復する。
おそらく橋の設計は山口が担当したのであろうが、山田守の直接関与抜きではこうした造形は実現
し得なかったであろう、・・そう思えてくる位山田らしいデザインが徹底している。

 現在の姿(2006年撮影)
現在の姿(2006年撮影)
現在の橋は首都高速道路上に架かるが親柱と欄干など一部分が復元され、新設のポケットパーク
(千田橋公園)と共に整備されていた。後でこれだけの整備するのには相当の費用を要したであろう。
どういうわけか、放物線状オブジェの部分が往時の姿に再現されていなかったのが残念である。
わくら橋
設計:復興局............................場所:東京都江東区......................................建築年代:1925(大正14)年頃?................................................親柱のみ現存


橋自体は既に無いが、表現派風親柱のみが保存されている。
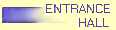
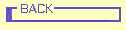
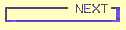






 竣工当時の姿(「建築写真類聚」より)
竣工当時の姿(「建築写真類聚」より)

 現在の姿(2006年撮影)
現在の姿(2006年撮影)