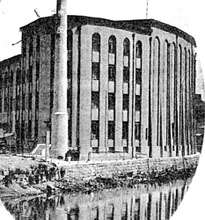 ....
....
邦楽座(「建築画報」VOL.16 1925(大正14)年7月号より)
遥か以前に失われてしまった1920年代を中心とする建築の記憶をここに留めておこうと思います。 この時代のいわば過渡期の建築は、未完の様相として忘れられがちです。しかし様々な思いを込めつつ、 近代化に向う時代状況を捉えて形にしようと苦闘した足跡は、今日でも参考にすべき点があるかも知れ ません。 そんなことを考えつつしばしタイムスリップしてみましょう。 |
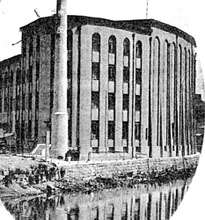 ....
....
有楽町の駅前、朝日新聞社に並ぶように建ち外壁一面に連続するアーチが埋め立てられる以前の外 堀の水面に反映するという趣向だった。この建物の設計を担当した阪東義三は分離派の面々とは同 級生でそのせいか表現派的でもある。単一のモチーフで徹底する造形は卒業制作にも見られるよう に彼の個性の表れか?。 阪東義三の活躍は東京市の営繕課に籍を置いて復興小学校の設計に関与したことが知られている。 |

大阪管区気象台は昭和48年に移転するまで大阪市生野区勝山で観測業務を行っており、この震計 室もこの地に昭和3年に竣工した。(註1) 本家ワイマール政権下のドイツの表現主義的雰囲気をよくここまで日本の地で再現したものだと感 心し、メンデルゾーンのアインシュタイン塔の強い影響に基づいた自由曲面に圧倒される。当然施 工の苦労も並大抵ではなかったものと想像する。 今のところ設計者は大阪府営繕課である以外に不明だが、建物存否の如何を問わず担当者個人名が 知りたい建物である。 |
註1:過去にある文献では、昭和8年の竣工と誤って伝えられたが、それは 後に地震計室に隣接して建てられた気象台本館の竣工年代である。 |

南大阪教会に次ぐ村野藤吾が独立して間もない頃の建築。本来ゼツェッションなどを得意として いた村野であったが長く勤めた渡辺節の元では許されず歴史主義建築を手掛けており、新しい造 形の方法を試行し自らのものにしようという意欲が漲らせてほぼ南大阪教会に次いで計画された。 壁面の扱旧来の様式建築の持つ物質性や厚みを消去して抽象的で薄い曲面に見える工夫を施すな ど、シュタイナーやメンデルゾーンらの表現主義建築を研究したように感じられる。しかもこれ は日本で表現主義風造形を徹底させた建築としては突出して大規模な建物で、その後の村野の活 躍を予感させるのにも十分だ。 (しかし村野にとってはこの建物はあくまで習作の部類だったのだろうか?。彼の数多い作品集 でも滅多に扱われることがない) あやめ池温泉は、大阪電気軌道(大軌)の開発による劇場と温泉を備えた総合娯楽施設として作 られた。(「あやめ池温泉余興場」とも称された) 戦争により米軍の接収を経た後は大阪松竹歌劇団(OSK)の学校として使用された時期があったよ うだ。現在、ここで往時の賑わいを想像することは難しい。 |

昭和2年12月、浅草―上野間に日本初の地下鉄が開通した。しかしこの時は完成していた地下鉄入口は 稲荷町のみで他は仮出入口のままであり、後に震災復興と歩調を合せて建設された。 駅ごとにデザインを変えるる配慮がなされており、事前に設計コンペが行われて決められた(註1)。 浅草の地域特性に沿ったデザインのほかアール・デコや表現主義など時流のデザインも織り込まれたよ うである。 |

浅草,上野,稲荷町―上の写真の部分は今も各地下鉄駅に残る(撮影1982年頃) |
地下鉄のデザイン深く関与した今井兼次は、早稲田大学の出身で分離派に相次いで「メテオール」を発 足させたメンバーとして知られる。現在も残る早稲田大学図書館の設計を終えた後、地下鉄設計のため 欧州を視察した。この視察の際にガウディなどを日本に紹介したことが知られる。 今井は欧州で得た知見をもとに、暗い地下を親しみやすい空間に演出するために地下鉄構内の壁面に歌 舞伎役者の家紋をあしらったものであろう。またアール・デコ装飾があしらわれ現存する稲荷町駅上屋は 今井の設計とある。(註2) |
註1,2:東京再発見―土木遺産は語る―(伊東孝,岩波新書)による。 |
